仕事をやっているつもりで、それをただの作業にしてしまうと、作業はやり甲斐に乏しく喜びや誇りを得ることが難しい。目的を明らかにして目的に向かうことで仕事の喜びと誇りを取り戻す。3人のレンガ職人の事例で示す。
「作業」と「仕事」の違い
仕事と作業の違いを考えてみたい。仕事をしているつもりでいつの間にかこれを作業にしてしまっているケースは多い。この違いを理解し作業を仕事に戻すだけで仕事の成果は格段に上がる。
「作業」とは
一般に作業とは考えなくて良い決まった手順に従って動作をすることと定義。この多くの場合で自分のやっていることの目的を意識できていない。動作が本来の目的に繋がっていない状態。
目的のわからない動作はつまらない。作業した結果が、本来の目的にどう貢献できたか?自分で実感することができない。結果、この作業はやりがいを感じることが難しい。それでも人は自分のやっていることに意味を持たせたくなる。ともすると「早く済ます」ことを意識し始める。「その作業を早く済ます事」を目的にしてしまう。
加えて、目的を意識しない作業は工夫に繋がらない。そもそも目的を意識していないので作業方法に工夫を加えて変えて良いかどうか?判断がつかない。
結果、同じ動作を繰り返す作業から抜け出すことができない。作業は単に収入を得るための「必要悪」となり「苦痛」と化してしまう。
「仕事」とは
一方、その目的を意識している動作は仕事とすることができる。目的を意識しているから自分で自分の仕事の結果を本来の目的に対する「成果」から知ることができる。この「成果」は「やりがい」を生む。
また目的を意識しているからこそ、その目的をより良く、より効率良く達成するための「工夫」が生まれる。「工夫」は「改善」を生み「より良い成果」を生む。周りからも評価され、やりがいをさらに高める正のフィードバックループが回り始まる。こうやって一度、このループに入ると、活き活きと仕事を楽しむ「仕事のできるやつ」が生まれる。
3人の煉瓦職人の話
旅人が旅の途中で次々に3人の煉瓦職人に出会う。それぞれの煉瓦職人に「あなたは何をやっているのか?」と問う。
- 1人目の職人の答え:見ての通り煉瓦を積んでいる
- 2人目の職人の答え:私は壁を作っているんだ
- 3人目の職人の答え:私は人々の祈りの場である大聖堂を作っている
1人目の職人は煉瓦を積む作業をしている。一方、3人目の職人は仕事をしている。3人目の職人は「大聖堂」を作っている。この仕事はやりがいを感じることができる。彼は、より良い「大聖堂」を作るための工夫を次々に行う。
35年間、企業戦士としていても、ふと、今自分がやっていることの目的を見失い作業に貶めてしまっていることに気づくことがある。そんな時には、もう一度「自分は何のためにこれをやっているのか?」を問い直す。
- 自分は「壁を作るために」煉瓦を積んでいないか?
- 自分の中に「出来上がった大聖堂」をありありと描けているか?そこで祈りをあげている人々が見えているか?より良い大聖堂を作ろうとする工夫に喜びを感じているか?そんな自分に誇りに満ちているか?
こう考え直すことで、仕事の喜びと誇りを取り戻すことができる。

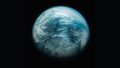

コメント